赤ちゃんの疾患ページ(出生後〜3, 4 か月頃)
停留精巣と移動性精巣について
今回は、「停留精巣と移動性精巣」について解説いたします。
停留精巣とは
停留精巣とは、生まれた赤ちゃんの精巣(睾丸)が、正常な位置である陰嚢(玉袋)に降りてきていない状態のことを言います。通常は、お母さんのお腹の中にいる間に陰嚢内に降りてきますが、途中で止まってしまうことがあります。正期産で生まれた赤ちゃんの約3〜5%にみられ、多くは生後3〜6か月以内に自然に降りてきます。しかし、1歳を過ぎても降りてこない場合は、小児科で詳しい診察が必要です。
移動性精巣(遊走精巣)とは
移動性精巣とは、一度正常に陰嚢に降りた精巣が、刺激や寒さなどによって一時的に太ももの付け根付近(鼠径部)に引き上がってしまう状態です。お風呂に入ったときや寝ている時など、リラックスした状況では再び陰嚢内に戻ることが特徴です。通常、これは心配のいらない現象であり、成長に伴って自然に落ち着くことがほとんどです。
症状と気づき方のポイント
停留精巣は痛みがないため、お子さんが自分で訴えることは難しいです。多くはおむつ替えや入浴中に、「片側の精巣が見当たらない」「左右の精巣の大きさや形が異なる」などの違和感で保護者が気づきます。また乳幼児健診で気づかれることもあります。
なお、停留精巣では「鼠径ヘルニア(脱腸)」や「精巣捻転(睾丸がねじれること)」を合併することがあります。急に陰嚢が腫れたり痛がる場合は、すぐに医療機関を受診してください。
診断と治療:停留精巣は手術が必要?
停留精巣が疑われる場合、小児科や泌尿器科の専門医が触診や超音波検査を用いて精巣の位置を確認します。生後6か月までは自然に降りる可能性があるため経過観察しますが、それ以降も改善しない場合には「精巣固定術」という手術を行います。手術の適切な時期は1歳~1歳半頃で、この時期を逃すと精子を作る機能が低下したり、将来的に精巣腫瘍(がん)のリスクが高まるため、適切な時期に治療を行うことが非常に大切です。
移動性精巣への対応
移動性精巣の場合は、基本的に治療は必要ありません。お子さんが成長して筋肉が安定すると、自然に陰嚢内に定着することが多いです。ただし、陰嚢内に全く降りなくなってしまった場合は、「挙上精巣」と呼ばれ、停留精巣と同じく治療が必要になることもあります。不安な場合は医療機関で相談し、定期的な経過観察を受けましょう。
停留精巣を放置するとどうなる?
停留精巣を治療せずに放置すると、精子を作る機能が低下し、将来の不妊症につながる可能性があります。また、精巣腫瘍(精巣がん)の発症リスクが少し高くなるとも言われています。さらに、精巣捻転など緊急を要する合併症のリスクも高まります。早めに対応すれば、こうしたリスクはほとんど避けることができますので、気になったら早めに受診しましょう。
ご家庭で気をつけること
日頃からおむつ替えや入浴時に陰嚢をチェックして、精巣が両側ともあるか、位置や大きさに違和感がないかを確認しましょう。「片方が見つからない」「精巣が動く」という場合は、メモをしておき、診察時に伝えてください。ただし、精巣を無理に引っ張って降ろそうとするのは危険ですので、絶対に避けてください。
迷ったら当院にご相談ください
移動性精巣と停留精巣の区別は難しいことがあります。気になる点があればお気軽にご相談ください。当クリニックでは、診察、超音波検査を行い、必要に応じて専門の病院とも連携しながら、保護者の方とお子さんに安心していただけるようサポートしています。

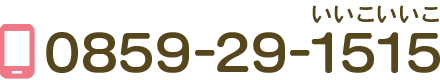



 診療時間
診療時間 電話
電話 Web予約
Web予約 アクセス
アクセス