小児科
マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎は子どもに多く見られる呼吸器感染症で、特に5歳から14歳のお子さんに多い病気です。
マイコプラズマ感染症は、肺炎マイコプラズマという病原菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。別名「歩く肺炎」とも呼ばれ、比較的軽症で済むことが多いため、感染に気づかないまま日常生活を送ってしまい、感染を広げるリスクがあります。
1.主な症状
マイコプラズマ肺炎では、以下のような症状が見られることがあります。
- 咳(特に乾いた咳が特徴で、熱が下がった後も数週間続くことが多い)
- 発熱(軽度~中等度)
- 頭痛やだるさ(倦怠感)
- のどの痛みや鼻水
- 胸の痛み
- 耳の痛み(中耳炎合併時)
お腹の不調など、症状が風邪に似ている場合もありますが、咳が長引く場合は注意が必要です。
注意すべき重症化のサイン
以下の症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください:
- 呼吸困難や息苦しさ
- 持続する高熱(39度以上が3日以上)
- 意識がもうろうとする
- 水分が取れない
- ぐったりして活気がない
2.検査 マイコプラズマ肺炎の診断や重症度に関して、必要な検査を行います。
1)病原菌検査(主に感度の良いPCR検査を行います):鼻やのどの粘液から、マイコプラズマ菌の遺伝子を検出する確定診断法です。最近増加している「マクロライド耐性菌(ある種の抗菌薬が効きにくい菌)」の有無を調べることもあります。
検査時間:検査法によって異なり、20〜60分程度です。
2)血液検査: 炎症の程度を調べます。
3)胸部X線検査: 肺の状態を調べる検査です。特徴的な影が現れることがあります。
3.治療方法
マイコプラズマ肺炎の治療には、抗菌薬が使われます。お子さんの症状や検査結果に基づいて、以下の薬が処方されます。
- マクロライド系抗菌薬(第一選択): 子どもに多く使用される安全な薬です。
- キノロン系抗菌薬: 重症例や耐性菌が疑われる場合に用いられます。
- テトラサイクリン系抗菌薬: マクロライド系が効かない場合や使えない場合に選択されます。ただし、8歳未満の使用は避けられます。
※マクロライド系抗菌薬に効かない「耐性菌」が増加しているため、治療が長引く場合は耐性菌を疑い、適切な薬に切り替えることがあります。当院では、迅速な診断検査、流行状況により、適切な治療法を選択しています。通常治療開始後2~3日で改善が見られることが多いです。効果が確認できない場合は「耐性菌」の可能性を考えて抗菌薬を変更することもあります。
4.予防するためには?
マイコプラズマ肺炎の感染予防には、以下のポイントを心がけましょう。
- 手洗いを徹底する: 外出後や食事前など、こまめな手洗いが大切です。
- 咳エチケットを守る: 咳やくしゃみをする際に、口と鼻を覆うようにしましょう。
- 人混みを避ける: 感染が広がりやすい場面をできるだけ避けることが有効です。
- 環境整備:室内の適切な換気(1時間に1回、5〜10分)、加湿器で湿度50〜60%を維持
5.家庭内感染を防ぐ対策
①感染者がいる場合
- 隔離期間:解熱後48時間まで
- 看病する人を1人に限定
- タオル、食器の共用を避ける
- 感染者は可能な限り個室で過ごす
- 家族全員のマスク着用
②兄弟姉妹への対策
- 症状がない場合も2週間は経過観察
- 発熱や咳が出現したら早期受診
- 学校・園への登校・登園判断は医師に相談
6.学校、保育園/幼稚園の出席停止基準
出席可能となる条件:
- 発熱が解熱していること
- 激しい咳が治まっていること
- 全身状態が良好であること
注意:軽い咳が残っていても、上記条件を満たせば登校・登園可能です。
7.当院での診療
お子さんの咳や発熱が続く場合、早めの受診をお勧めします。当院では、最新の検査機器を使用し、迅速かつ適切に診断・治療を行っています。お子様の健康を第一に考え、丁寧なケアを心がけていますので、気になる症状がある場合はお気軽にご相談ください。

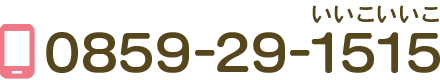



 診療時間
診療時間 電話
電話 Web予約
Web予約 アクセス
アクセス