乳児湿疹について
クループ症候群について
最近クループ(クループ症候群)を発症するお子さんが少し増えているように思われます。要因ははっきりとしていませんが、検査でRSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、パラインフルエンザウイルスなどが陽性となるお子さんが時々あるため、このような感染症が関連している可能性があります。
クループ症候群は、主に生後6ヶ月から3歳の乳幼児に多く見られる呼吸器の病気で、 3歳までのお子さんに多く発症しますが、年長児や小中学生にみられることもあります。 これは、乳幼児の喉頭や気管が大人よりも狭く、炎症による腫れで気道が閉塞しやすいためです。
「クループ」の意味は?
「クループ(croup)」という呼び名は、喉から出るしゃがれた声や咳の音を擬音化した英語(「馬のように鳴く」という意味の動詞「croup」)に由来しており、その医療的現象を呼び表す言葉として定着したものです。
クループ症候群になりやすい子どもの特徴
-
年齢:生後6ヶ月から3歳の乳幼児に多く見られます。
-
アレルギー疾患の有無:アレルギー性鼻炎や気管支喘息などのアレルギー疾患を持つお子さんは、感冒時にアレルギー反応が併発し、喉の粘膜が腫れやすくなるため、クループ症候群を発症しやすいとされています。
クループ症候群の原因
主な原因はウイルス感染で、特にパラインフルエンザウイルスが多いとされていますが、他にもRSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、インフルエンザウイルスなどが原因となることがあります。
クループ症候群の症状:録音・録画での記録があると診断しやすいですので、クループ様の咳と思われる時は記録をお願いします。
・犬吠様咳嗽:犬が吠えるような特徴的な咳が見られます。
・嗄声:声がかすれることがあります。
・吸気性喘鳴:息を吸うときに「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音がすることがあります。
これらの症状は夜間や寝ている時、大きな声で泣いた時に悪化しやすいことが特徴です。
クループ症候群の治療
・薬物療法:喉頭の腫れを改善させるためにステロイドの内服を行います。
・吸入療法:アドレナリン(ボスミン)やステロイドを含んだ吸入を行うことがありますが、効果の持続は短時間であるため、症状が再燃することがあります。
自宅でのケア
・加湿:加湿器や洗濯物などで充分な加湿をしてください。
・安静:大泣きをきっかけに症状が悪化することもありますので、安静を保つように心がけてください。
注意が必要な症状
以下の症状が見られる場合は、緊急を要する可能性があるため、すぐに医療機関を受診しましょう。
・息を吸うときに喉の付け根や胸をへこませる呼吸(陥没呼吸)をしている
・顔色や唇の色が悪い
・水を飲み込めず、よだれが出ている
・息苦しくて横になっていることが出来ず、起き上がってしまう
クループ症候群は、適切な治療とケアで多くの場合、数日から1週間程度で回復します。しかし、症状が重い場合や呼吸困難が見られる場合は、早急に医療機関を受診しましょう。
当クリニックのご案内
当クリニックでは、クループ症候群をはじめとする小児の呼吸器疾患に対応しております。ご不明の点などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
スギ花粉の飛散がはじまります
赤ちゃんのでべそ(臍ヘルニア)について
四種混合ワクチンの予防接種が完了していないお子さまへ
令和6年4月から五種混合(四種混合+ヒブ)ワクチンが定期接種となったため、四種混合ワクチンの製造が終了となりました。
令和7年7月頃までは、四種混合ワクチンの在庫がある見込みですが、不足する可能性がありますので母子手帳を確認し、対象となるお子さまは早めに接種しましょう。
※四種混合ワクチンの追加接種(4回目)は、標準的には初回接種3回目終了後から12~18か月までに接種することが推奨されていますが、6か月以上あけて接種することも可能ですので早めの接種をご検討ください。
※四種混合ワクチンの在庫がなくなった場合
① 四種混合ワクチンとヒブワクチンの接種回数が同じ場合は、五種混合ワクチンへ切り替えて接種します。
② 四種混合ワクチンとヒブワクチンの接種回数が異なる場合は、五種混合ワクチンへ切り替えが出来ませんのでご相談ください。
ご不明な点や心配なことがございましたらご相談ください。
4月から小学校・中学校入学のお子さまへ
小学校、中学校生活が始まると予防接種を受ける機会が少なくなります。まだ受けておられない予防接種があるお子さまは早めに受けましょう。
定期接種(無料)は年齢制限がありますので母子手帳を確認し早めにご予約ください。
★小学校入学までに終わらせておきたい予防接種
定期接種(接種年齢に制限があります)
●MR(麻しん風しん)2期・・就学前(年長)
●日本脳炎1期追加・・7歳半まで
任意接種(私費)
●おたふくかぜ2回目
★中学校入学までに終わらせておきたい予防接種
定期接種(接種年齢に制限があります)
●2種混合・・11歳~13歳まで
●日本脳炎2期・・9歳~13歳まで
※子宮頸がんワクチン(小学校6年生~高校1年生相当の女性)についてもホームページに記載しておりますのでご覧ください。
子宮頸がんワクチンについて➡ コチラ
ホームページ予防接種について➡https://www.kosodate-nagata.jp/medical/vaccin
★ 定期接種は接種の時期を過ぎていても任意接種(私費)として受けることが出来ます。
★ その他にもまだ受けておられない予防接種があるお子さまは早めにご相談ください。
HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種の経過措置(期間延長)について
対象となる方は2025年3月31日までに第1回目の接種が必要です
子宮頸がんを予防するためのHPVワクチンは、定期接種の対象者だけでなく、過去に接種機会を逃した方を対象としたキャッチアップ接種が実施されています。現在、国の方針により、対象者には無料で接種できる機会が設けられています。
2025年(令和7年)3月31日までが対象期間となりますので、該当する方はぜひ早めに接種をご検討ください。
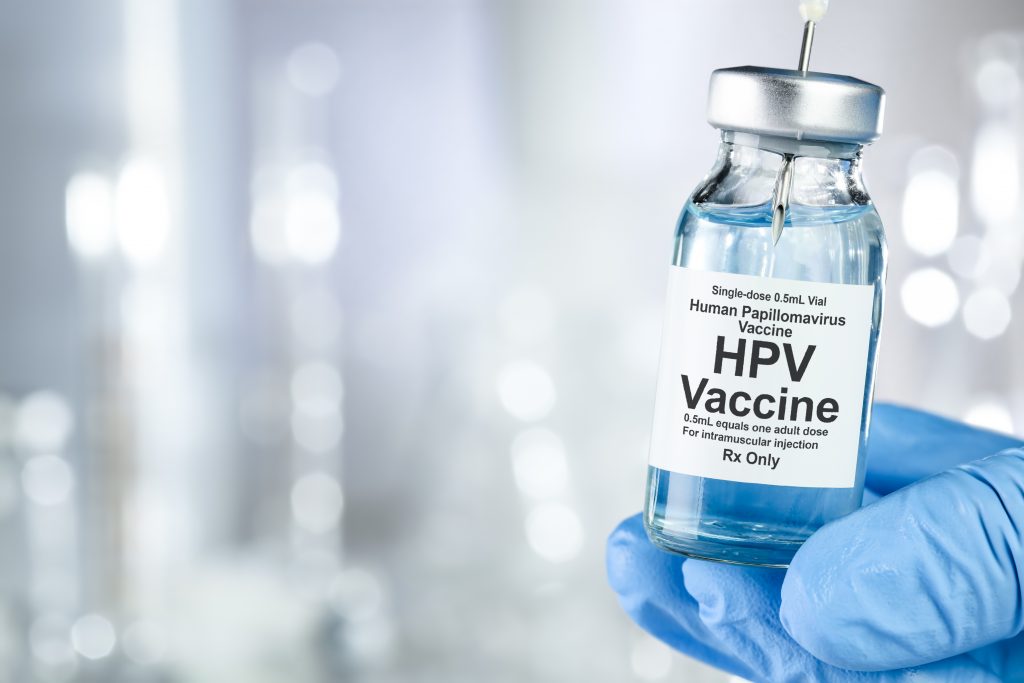
経過措置の対象者
以下の条件に当てはまる女性が対象です。
✅ 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性(キャッチアップ対象者)
✅ 平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性(高校1年生相当)
✅ これまでにHPVワクチンを1回も接種していない、または規定回数(3回)を完了していない方
対象者には自治体から案内のハガキが送付されています(自治体によって送付時期は異なります)。
接種スケジュールと費用
HPVワクチンは全3回の接種が必要です。
💉 1回目 → 2回目(2か月後) → 3回目(6か月後)
キャッチアップ接種の対象者は無料で接種できます。ただし、上記対象の方であっても、第1回目の接種を2025年3月31日までに接種されてない場合は自己負担となりますのでご注意ください。
ワクチンの種類
当クリニックでは9価ワクチン(シルガード9)を接種しています。
接種を受けるには?
1️⃣ お住まいの自治体から届く案内ハガキを確認
2️⃣ 小児科や婦人科で予約(当院でも接種可能です)
3️⃣ 接種当日は母子手帳や接種記録を持参
過去の接種歴を確認し、適切な回数を接種しましょう。
HPVワクチンの副反応について
HPVワクチンは一般的に安全性が高いとされていますが、接種後に以下の副反応が出ることがあります。
🔹 注射部位の腫れや痛み
🔹 発熱
🔹 頭痛・倦怠感
まれにアレルギー反応(アナフィラキシー)を起こすことがあります。接種後はしばらく院内で安静にし、体調の変化がないか確認しましょう。
まとめ
HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるウイルスの感染を防ぎ、将来的な健康を守る大切なワクチンです。キャッチアップ接種の対象の方で、接種開始時期は2025年3月31日までとなっていますので、該当する方は早めに接種を検討しましょう。
当院でもHPVワクチンの接種を受け付けています。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の動向(新型コロナウイルス感染症が増加傾向です)
インフルエンザ警報が解除されました(令和7年2月5日)
新型コロナは増加傾向です(鳥取県西部は注意報レベルです)
全国的にインフルエンザの流行は落ち着きつつあり、鳥取県でも1医療機関あたりの患者数が10人未満となっています。
一方、新型コロナウイルスは全国的にやや増加傾向にあり、鳥取県では1医療機関あたり約8人、特に西部地域では10人を超え、注意報レベルに達しています。成人の感染が増える中、小児の感染例も増加がみられます。家庭内での感染に加え、学校や保育園でも小規模な流行が発生しています。
子どもの症状は、発熱、鼻水、咳など、風邪に似たものが多く、発熱は1日で解熱することも少なくありません。
感染予防と受診のポイント
感染予防のために、手洗い・うがい・マスクの基本対策を徹底しましょう。また、体調がすぐれないときは早めに休息をとり、必要に応じて医療機関の受診を検討してください。
発熱時の受診について
当院では、発熱のある患者さんを感染症用の診察室で診察しています。診察時間に特別な制限はありませんので、ご不安な場合はご相談ください。
また、新型コロナウイルスの検査には、一般的な抗原検査、核酸増幅検査(NEAR法)、ウイルス・細菌多項目の核酸増幅検査を実施しています。
発熱時、発熱直後はウイルス量が少なく検査で検出されにくいため、できれば半日以上経過してから受診すると、検査の精度が高まり、より正確な診断が可能になります。
今後も流行状況に注意しながら、適切な感染対策を続けていきましょう。
アレルギー疾患に対する生活管理指導表について
学校や幼稚園、保育園では、アレルギー疾患をお持ちのお子さんに対して**「生活管理指導表」**の提出が必要です。すでに学校や園から書類を受け取られている方もいらっしゃるかと思います。
この手続きは、お子さんが学校や園で安全に過ごすためにとても重要です。提出を忘れないようご対応ください。
「生活管理指導表」の詳細については、以下のリンク先で詳しくご説明していますので、ぜひご参照ください。(→学校、園におけるアレルギー疾患に対する生活管理指導表について)

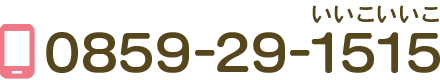



 診療時間
診療時間 電話
電話 Web予約
Web予約 アクセス
アクセス