年末年始のお知らせ
12月27日(土) 通常通り
12月28日(日) 休診
12月29日(月) 休診
12月30日(火) 休診
12月 31日(水) 休診
1月 1日(木) 休診
1月 2日(金) 休診
1月3日(土) 休診
1月4日(日) 休診
1月5日(月) 通常通り
【年末年始 小児科輪番表】
※急に変更になる場合がありますので、お電話でご確認ください。
12月27日(土)山陰労災病院(17:00~22:00)
12月28日(日)米子医療センター(8:30~17:00)
12月29日(月)米子医療センター(8:30~17:00)
12月30日(火)山陰労災病院(9:00~17:00)
12月31日(水)米子医療センター(8:30~17:00)
1月 1日(木)山陰労災病院(9:00~17:00)
1月 2日(金)米子医療センター(8:30~17:00)
1月 3日(土)山陰労災病院(9:00~17:00)
1月 4日(日)米子医療センター(8:30~17:00)
※米子市急患診療所 12月28日(19:00~22:00)・12月29日~1月3日(9:00~22:00)
※上記以外の時間帯は鳥取大学医学部附属病院
【連絡先】
米子医療センター 0859-33-7111
山陰労災病院 0859-33-8181
鳥取大学医学部附属病院 0859-38-6699
米子市急患診療所 0859-34-6253
※急患診療所は内科医の場合がありますのでお電話して確認して下さい。

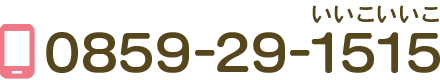


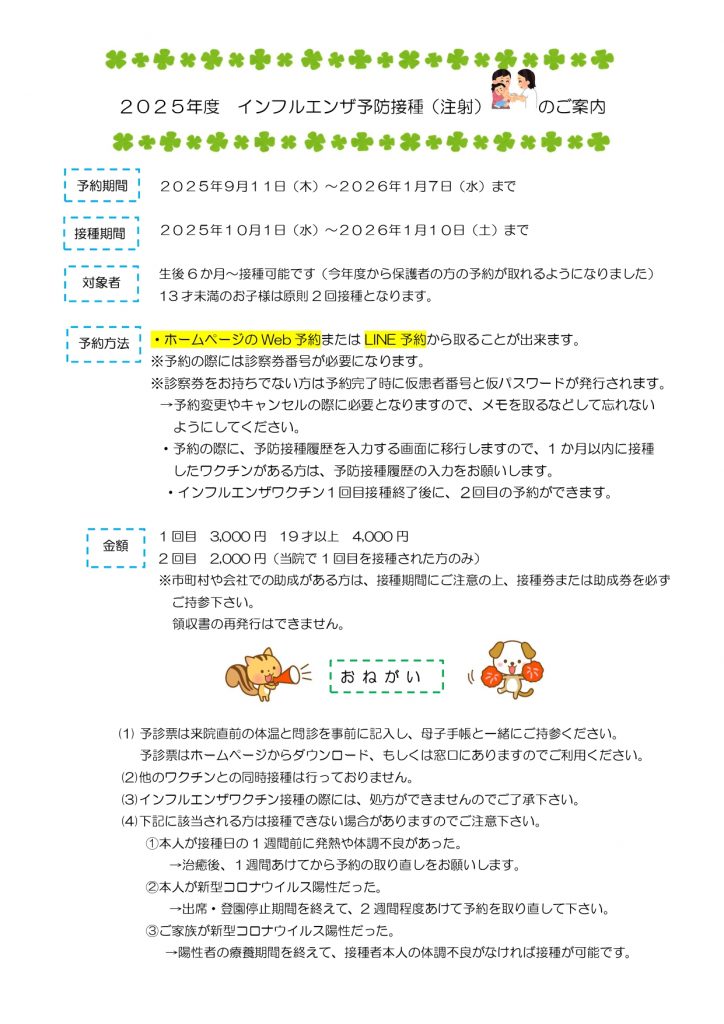
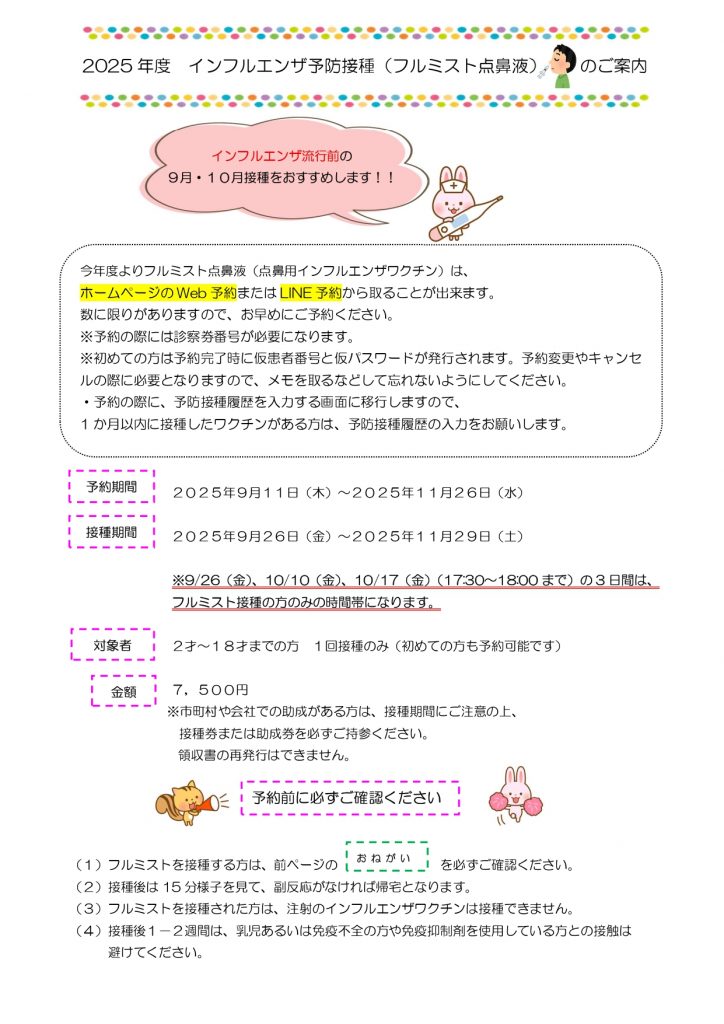


 診療時間
診療時間 電話
電話 Web予約
Web予約 アクセス
アクセス